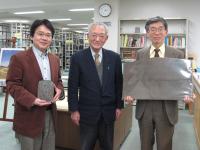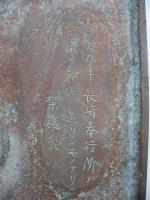同志社大学の秋学期に相当する期間、スカイプを使って、太平洋横断のゼミを行ってきましたが、この月曜日で無事すべての日程を終了することができました。
インターネット授業や、ポッドキャストによる授業などにこれまで取り組んできましたが、インターネットを利用したゼミは初めてだったので、私にとっても、よい経験となりました。
この経験を一応、まとめておきたいと思います。
1)接続形態
今回スカイプを利用しましたが、スカイプのビデオ接続は一対一という限界があります。たとえば、MacのiChatが使えれば、さらに人数を増やすことができるので、複数のカメラを教室に設置することも理論的には可能です。
当初、同志社大学での接続はWifi接続でしたが、途中、接続状態にムラが生じたため、LAN接続に切り替えてもらいました。やはり、LAN接続の方が、はるかに回線が安定しています。画質も音質も非常にクリアーになりました。
マイクは、MacBookの内蔵マイクを使用したため、どうしても距離の遠い人の声は聞こえにくくなりますが、それでも端の人の声も認識できる程度にひろってくれていました。
集音力の高い外部マイクを用意できれば、音質はさらにアップすることでしょう。
2)カメラと座席の配置
カメラでなるべく全員の姿が映るように座席を工夫してもらいました。その結果、菱形に座席を組むと、十数名の姿をすべて視界に入れられることがわかりました。
ただし、マイクの角度は固定されており、ズームはできませんので、一人ひとりの表情まではトレースすることができません。

3)インターネットゼミでの理想のガジェット
ここから一気にガジェット論へ!
スカイプでのゼミは十分に学問的討議に資するものでしたが、より双方向性を高めるためには、もう少しすぐれたガジェットがほしいところ。
私の理想は、WAAL・Eのような形状を持ち、小さな範囲を遠隔操作で動き回れると同時に、カメラの方向も自在に変え、ズームもできるようなものです。胴体の部分にはプロジェクターが内蔵されていて、近くの壁に私の姿(欲を言えば、3Dホログラフ)を映し出します。誰か、こんなガジェット作ってくれませんかね? 今の技術でも十分製作可能だと思うのですが、ありそうでないですね。